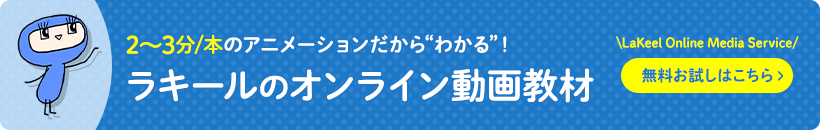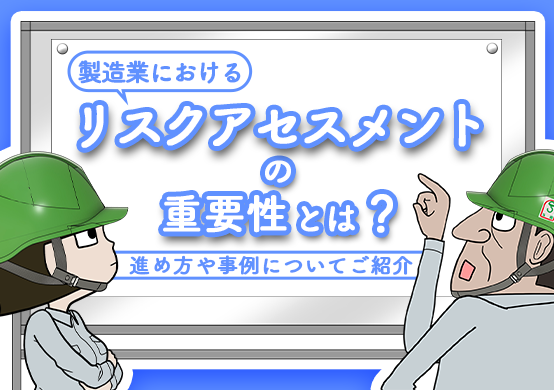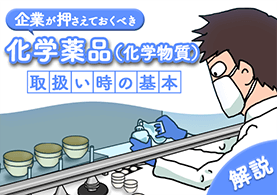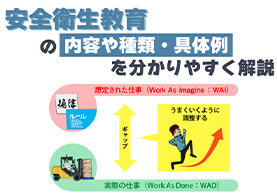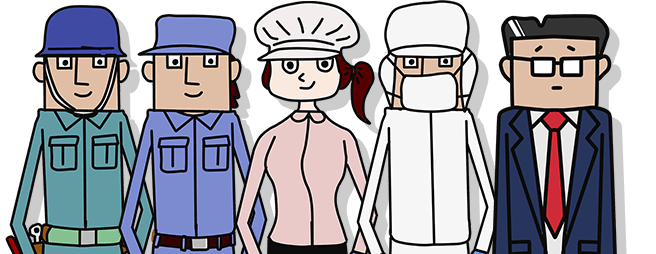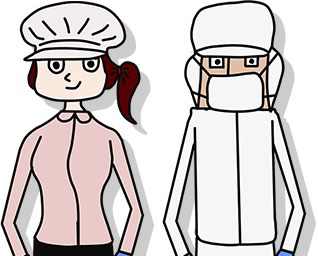労災かくしは労働災害が起きた際に作業者や職長などの現場責任者、企業が労働者死傷病報告を行わないなど、労働災害を隠すことを指します。労災かくしは、企業はもちろん、関係各者にも大きな損害を被ります。徹底した予防策を講じて労働災害を未然に防ぐとともに、発生時には労働災害を隠さず正しく報告する環境を整えることが重要です。
今回は、労災かくしの概要から具体的な該当する行動、労災かくしが発覚した際の罰則、労災かくしが起きる原因、企業における労災かくしのリスク、予防する方法を解説します。
労災かくしとは?
労災かくしの定義と厚生労働省の対応、罰則について解説します。
労災かくしとは
労災かくしとは、事業者が労災事故の発生を故意に隠すことを指します。
労働災害等により、労働者が死亡または休業した場合には、遅滞なく、「労働者死傷病報告」などを労働基準監督署長に提出しなければなりません。
労災かくしにおいては、労働者死傷病報告を
(1)故意に提出しないこと
(2)虚偽の内容を記載して提出すること
の2つが該当します。
書類の提出漏れではなく、労災事故を隠そうという事業者の明白な意図がある場合を労災かくしと呼んでいます。
また労働災害により労働者が負傷した場合などには、休業補償給付などの労災保険給付の請求を労働基準監督署長宛てに行う必要があります。休業4日未満の労働災害については、労災保険の給付対象外となるため、使用者が労働者に対し、休業補償を行わなければなりません。
労災を隠す場合、これらの労災保険給付の請求や休業補償も行わないことも多く、労働者にとって不利益を被ることになります。
厚生労働省の対応
厚生労働省は、労災かくしについて、適正な労災保険給付に悪影響を与えるばかりでなく、労働災害の被災者に犠牲を強いてまで、自己の利益を優先する行為であるとし、労働安全衛生法に違反し、罰則の対象であるとしています。罰則を適用し、厳しく処罰を求めるなど、厳正に対処することを示しています。
労災かくしを行った場合の罰則
労災かくしを行った場合の罰則は、50万円以下の罰金(労働安全衛生法120条第5号)とされています。
労災かくしが起きる原因
労災かくしが起きる原因はどのようなことにあるのでしょうか。事例をもとに見ていきましょう。
監督署等の調査・監督、処分を回避するため
労災かくしの事例では、何らかの事情で監督署等の調査・監督、処分を恐れ、それらを回避するために労働災害を隠した例が多くあります。
中小受託事業者(下請け)が元請(もとうけ)や発注者からの今後の受注を確保したいため
よくある根本の原因として、元請(もとうけ)や発注者からの今後の受注を確保したいために隠したというものがあります。
ある事例では建設現場で、作業員が作業中に転倒し、右手首を複雑骨折しましたが、「受注を確保するために、元請に労災保険で迷惑をかけたくない」として労働災害が起きたことを隠したと、後日、労働災害を起こした企業が明かしています。
労災保険のメリット制や、無災害記録等への影響を避けるため
労災保険には、過去3年間の労災発生状況などに応じて保険料率が増減する制度である「メリット制」があり、この制度を気にして労働災害を隠したケースがあります。
また一定期間、労働災害が起きなかった事業場には無災害記録証が授与されますが、この記録を保ちたいことを理由に発生を隠したケースもあります。
労災保険への未加入や他の法違反の発覚を避けるため
そもそも労災保険へ加入していない、他にも法に違反していることがあり、それらが発覚するのを避けたいといった理由で、労働災害の発生を隠すことがあります。
企業における労災かくしのリスク
労災かくしを行うと、企業はどのようなリスクがあるのでしょうか。主なリスクを見ていきましょう。
罰則が適用されるだけでなく、企業の信頼低下など多大な損害が出る
労災かくしが発覚した場合、重大・悪質な法令違反に対しては、労働基準監督署は司法警察権限を行使して捜査を行い、労働基準関係法令違反被疑事件として検察庁へ送検します。
罰則だけのリスクではなく、隠した職長や中小受託業者の監督者及び元請けの監督者も送検される可能性があり、起訴された場合は確実に有罪となるため、前科が付くことになります。
関係各者および世間からの信頼を大きく落とすことになり、顧客離れや取引継続の危機に陥ることになるでしょう。結果的に甚大な損害が出ることになります。
これらの損害を知っておかなければ人情や目先の利益にほだされて労災かくしを行ってしまいます。
労働災害の発生原因の究明や対策が正しく行えない
労働災害は、一度発生してしまったら、適切に対処し、今後二度と発生しないための取り組みを徹底することが重要です。そのためには、原因究明と対策が重要になりますが、労災かくしをしたままでは原因究明を適切に行えないため、対策も実行できません。再度、同じような事故が起きてしまう恐れがあります。
被災した従業員への補償に支障が出る
労働災害の発覚を恐れ、休業補償給付などの労災保険給付の申請も行わなければ、被災した従業員が重症だった場合に適切に治療が行えず、後遺症が残ってしまうケースもあります。
発覚すれば関係各者への責任追求も発生する
先に労災かくしの主な原因として元請や発注者からの契約打ち切りを恐れることを挙げましたが、労災かくしが発覚すれば、元請や発注者などの関係各者に対しても責任追求が発生します。かえって関係各者に損害や面倒をもたらすことになってしまうのです。
全従業員のモチベーション低下
労災かくしは、隠している間も、発覚後も、どちらも従業員のモチベーションが低下するでしょう。退職者が続出する恐れもあります。
企業が労災かくしを予防する方法とは
労災かくしは、未然に予防ができます。主な予防法をご紹介します。
目先の利益を優先する考え方を切り捨てる
多くの場合、「元請に迷惑がかかる」「小さい事故だったら黙っていたほうが良い」といった目先の利益を優先する考えが、労災かくしにつながっています。隠すことそのものや、発覚後の将来的な損害と事業存続リスクなどを総合的に考える必要があります。
企業の真摯な対応姿勢を従業員に見せる
労働災害は従業員の命にかかわることであることから、発生してはならないものと認識して、「発生ゼロ」を目指し、日頃から予防策を徹底することは重要です。しかし、どんなに気を付けていてもリスクがゼロになるわけではなく、どうしても発生してしまうことがあります。その場合は、元請けも含めて、従業員や関係各者に対して顔向けできないと考えるのではなく、正しく処理し、明日から災害を起こさないために頑張るといった姿勢が、重要なのではないでしょうか。そうすれば、従業員にも安心して働ける職場を提供できます。
あらかじめ労災かくしの事例を確認し、リスクを知る
労災かくしの送検事例は厚生労働省の公式サイトに公表されています。このような事例を複数確認し、どのような損害が生じるのか、具体的なリスクを知っておくことが重要です。
【関連リンク】
厚生労働省「『労災かくし』の送検事例」
労働災害が起こらない環境づくりと労働安全衛生教育に注力する
そもそも労働災害が発生しなければ、労災かくしも起こりません。労働災害が起こらないための環境づくりや労働安全衛生教育に注力することも重要な日頃の行いといえます。
まとめ
労災かくしは、自社のみならず従業員や関係各者にも甚大な損害をもたらし、企業の信頼を根本から揺るがす重大な問題です。その根本的な対策として、損害の規模やリスクを正確に把握するとともに、そもそも労働災害が発生しない仕組みを日頃から築いておくことが重要です。
また、労働災害を減らすためには、従業員一人一人の意識を高めることも有効です。
そこでおすすめなのは、“わかってもらえる”オンライン教材 LOMの安全衛生教育サービス「LaKeel Online Media Service」です。アニメーション動画による解説で、労働災害に関する教育効果も高めることができます。安全な労働環境づくりのために、ご活用ください。
サンプルムービー
動画も見てみる!

LaKeel Online Media Serviceの動画を
無料でお試しいただけます。
\1分で完了!すぐ見れる/