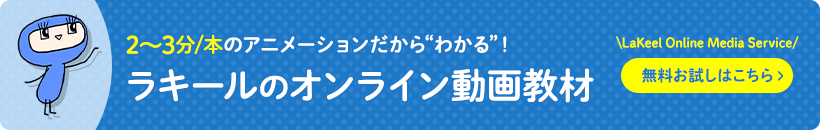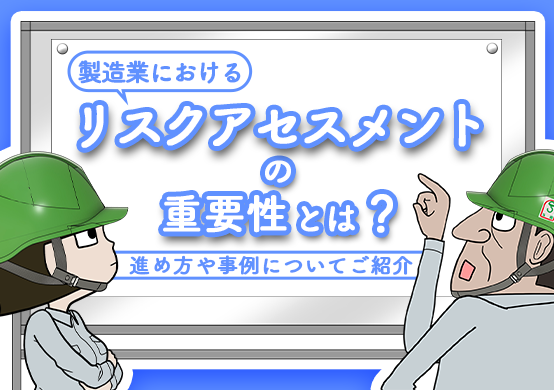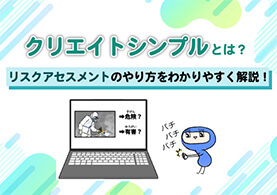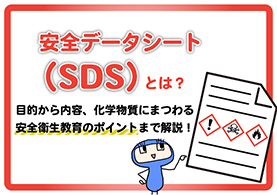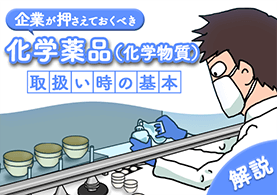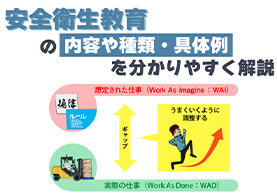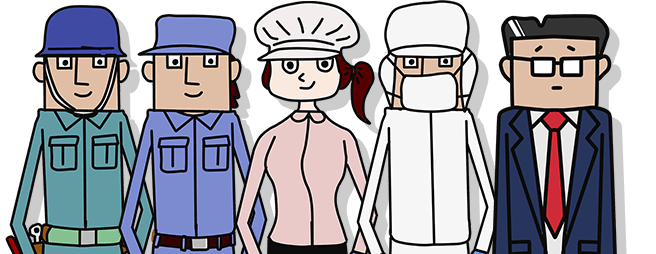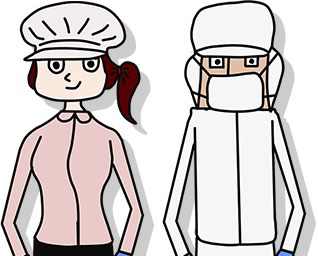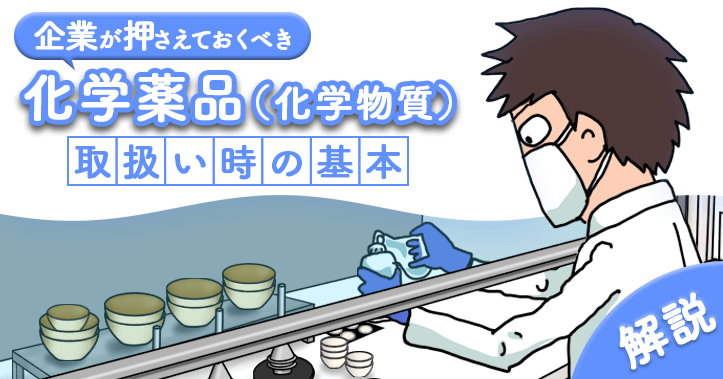
化学薬品をはじめとする化学物質は、労働災害の原因の一つとして注視されており、化学工業のみならず、食品製造業や、小売業・飲食店など幅広い業種でも労働災害が報告されています。化学物質が身近なところにある事業場では、特に取扱い時の基本を押さえておく必要があります。
今回は、企業における化学物質による労働災害の実態と事例、化学薬品を取り扱う際の基本事項、2022年5月に改正された労働安全衛生法における化学物質に関係する事項を解説します。
企業における化学物質による労働災害の実態
近年、企業において、化学物質による労働災害はどのくらい起きているのでしょうか。まずは実態をデータで見ていきましょう。
化学物質に関連性の強い労働災害の件数
厚生労働省の統計によると、化学物質の性状に関連の強い労働災害(事故の型が有害物質等との接触、爆発、火災によるもの)は、2014年から2023年の10年間で、年間500件前後で推移しています。減少している様子は見られないため、注意喚起がされています。
2023年は合計542件で、内訳は「有害物質等との接触」は463件、「爆発」49件、「火災」30件でした。
「有害物質等との接触」による労働災害の発生状況
「有害物質等との接触」による労働災害の分析結果において、業種別の発生状況を見てみると、最も多いのは、食料品製造業(162件)で、次いで化学工業(119件)でした。また小売業と飲食店を合わせると計134件となりました。
一般的に、有害物質を使用して労働災害が起きるのは化学工業や金属製品製造業に多いイメージがありますが、金属製品製造業は88件です。つまり、食料品製造業や小売業・飲食店のほうが多く発生していることがわかります。
製品別の発生状況では、「洗剤・洗浄剤」による労働災害が約3割(371件)と圧倒的に多くなっています。また「ガス」「消毒・除菌・殺菌・漂白」による労働災害も多い状況です。
作業別の発生状況では、「清掃・洗浄作業中」が約3割(382件)となり最多に。「移し替え・小分け・交換・補充作業中(124件)」「製造(110件)」「工事(107件)」「点検・修理・メンテナンス作業中(99件)」の順でした。交換・補充や点検などの非定常作業における労働災害の多さには注目しなければなりません。
出典:厚生労働省「化学物質の性状に関連の強い労働災害の分析結果」
化学物質による労働災害事例
化学物質による労働災害の事例を見ていきましょう。いずれも多い労働災害であるため、典型的な事例といえます。
食料品製造業 洗剤・洗浄剤による火傷
食品製造の厨房において、清掃・洗浄作業中の出来事です。作業者はフライヤーの油を洗うために次亜塩素酸ソーダ入りの薬品をスポンジにつけたところ、腕カバーを装着していなかったため、薬品が袖口から腕に伝わり、火傷を負いました。
化学工業 工程で使用する薬品による薬傷
化学工業の現場において起きた事例です。作業者はエポキシ棟内で、ドラム缶を持ち上げてハイライト製剤用の原料を小分け計量する作業をしていました。このとき、ドラム缶のふたを閉める際に原料がこぼれてしまい、左足甲部に付着したことで薬傷を負いました。
清掃業 清掃・洗浄による目の角膜化学腐食
一般住宅における清掃作業を行っていた清掃業の事例です。作業者は、一般住宅の流し台の排水管の詰まり除去の作業を行っていましたが、アルカリ性の洗浄剤を排水口に使用した際、汚れと洗浄剤が化学反応を起こし、液体が跳ねて目に入り、負傷しました。
企業における化学薬品取扱いの基本事項
化学薬品などをはじめとする化学物質関連の労働災害を減らすためには、各現場において、化学物質の取扱いについて、今一度、基本的な事柄を確認しておく必要があります。
ここでは企業における化学薬品の取扱いの基本事項を解説します。
化学薬品と法規制
化学薬品は、主に製造業における製造工程や、実験研究などに使用される化学物質です。化学物質の利用には法規制があり、遵守しながら適切な使用を進める必要があります。
労働環境に関係する法律として重要なのは労働安全衛生法です。労働安全衛生法では、化学物質による労働災害を防止するため、適切な取扱い方などが定められています。
労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成と促進を目的とするものです。そのうち、有害物による健康障害から労働者を守るための規定もあります。
化学物質による労働災害防止のため、事業者が実施すべきこと
労働安全衛生法においては、労働災害防止のため、事業者は事業場における自律的な化学物質管理が求められています。事業者が実施すべき基本ステップはこちらです。
1. 事業場で取り扱うすべての化学物質を把握する
事業場で取扱っているすべての化学物質をリストアップし、リスクアセスメント(※1)対象物であるかどうかを特定します。リスクアセスメント対象物とは、ラベル表示、SDS(※2)交付、リスクアセスメント実施が義務付けられている物質を指します。
※1 リスクアセスメント:リスクアセスメント対象物の危険性・有害性を特定し、その特定された危険性・有害性に基づくリスクを見積もり、その結果に基づいてリスク低減措置を検討する一連の流れのこと。
※2 SDS:Safety Data Sheetの略で、安全データシートと訳される。化学物質や化学物質を含む混合物を譲渡または提供する際に必要な情報を含む文書のこと。
2. 体制を整備する
リスクアセスメント対象物を製造・取扱い・譲渡・提供する場合は、化学物質管理者の選任が必要です。また、化学物質から身を守る呼吸用保護具などを継続的に使用する作業がある場合は保護具着用管理責任者の選任が必要です。
3. リスクアセスメントを実施する
リスクアセスメント対象物に対するリスクアセスメントを実施します。
4. その他の実施事項
その他にも、労働者への教育、ラベル表示、SDS交付、がん原性物質への対応、有害性等の掲示、労働災害時の対応といった取り組みも必要です。
詳細は、(独)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の職場の化学物質管理総合サイト「ケミサポ」の「自律的な管理を進めるための4つのステップ」で詳しく解説されていますので、確認してください。
【関連リンク】
ケミサポ「自律的な管理を進めるための4つのステップ」
労働安全衛生法改正に伴う化学物質に関係する事項
2022年5月に労働安全衛生法の一部が改正され、化学物質による労働災害を防止するため、新たな規制が加わりました。
主な内容として、次のことが挙げられます。
リスクアセスメントの実施義務対象物質が大幅に増加
国によるGHS分類で危険性・有害性が確認されたすべての物質が順次追加されます。法令改正前のリスクアセスメント対象物の数は674物質でしたが、2026年4月時点で予定されているリスクアセスメント対象物の数は、約2,300種類(※3)にも上ります。これまで対応が不要だった化学物質に関しても対応が必要になることがあります。
※3 出典 ケミサポ
労働者がばく露される濃度を基準値以下とすることが義務付け
リスクアセスメントを実施した後、その結果を踏まえて、労働者がそのリスクアセスメント対象物にばく露される程度を、最小限度にすることが義務付けられました。
加えて、厚生労働大臣が定める物質(濃度基準値設定物質)については基準値以下とすることが義務付けられました。
適切な保護具の使用
皮膚などへの障害を引き起こし得る化学物質を製造・取り扱う労働者に対しては、適切な保護具を使用させる必要があります。
自律的な管理に向けた実施体制の確立
事業者は、これまで以上に自律的な管理が求められています。化学物質管理者や保護具着用管理責任者の選任義務化や、リスクアセスメント結果等の記録作成・保存などが挙げられます。
まとめ
化学物質による労働災害は、化学工業だけでなく食品製造業や小売・飲食業など幅広い現場で発生しており、決して他人事ではありません。事業者は、リスクアセスメントの実施や体制整備、法改正への対応などを通じて、化学物質管理を自律的に進めていく責任があります。
そのうえで、労働者一人ひとりが危険有害性を理解し、安全に作業できるように教育することが欠かせません。教育を継続的に実施することで、労働災害の未然防止につなげましょう。
「LaKeel Online Media Service」では、労働安全衛生に関する幅広い動画コンテンツを提供しており、化学物質に関する教育コンテンツも数多く取り揃えています。わかりやすく印象深いアニメーション動画により、従業員の理解度を深めることが可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。
サンプルムービー
動画も見てみる!

LaKeel Online Media Serviceの動画を
無料でお試しいただけます。
\1分で完了!すぐ見れる/