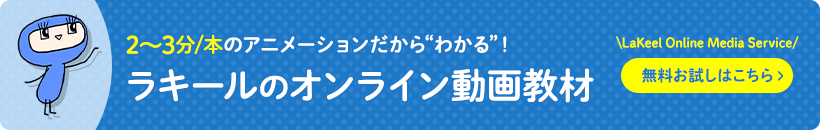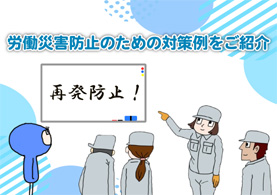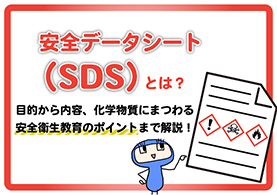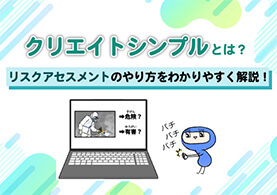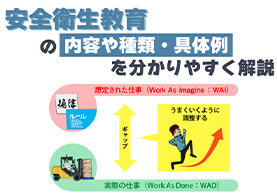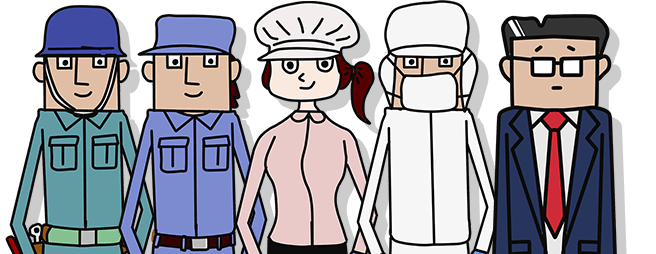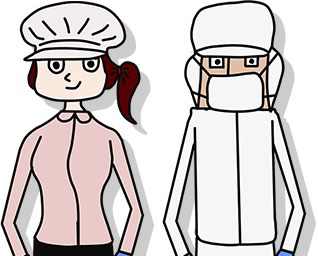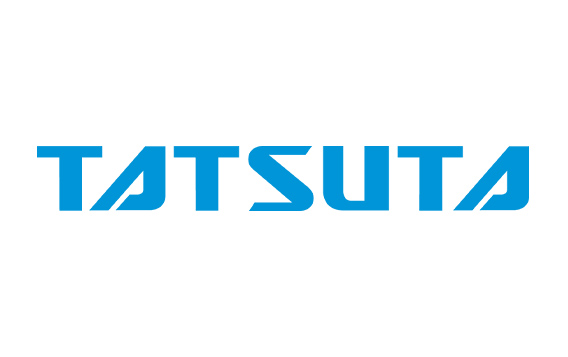今年も7月1日から7日まで、全国安全週間を迎えます。6月中は準備期間とされていることから、毎年6月から7月は労働災害の防止活動に力を注いでいるのではないでしょうか。今回は、全国安全週間の概要から、実施内容、自主的な労働災害防止活動の事例をご紹介します。
全国安全週間とは?
全国安全週間の概要をご紹介します。
全国安全週間とは?
全国安全週間とは、毎年7月1日から7月7日に厚生労働省と中央労働災害防止協会が主唱者として実施される労働災害防止活動の推進を図るためのキャンペーンで、労働安全衛生に関する意識を高め、労働災害を防止することを目的として実施される1週間のことを指します。
全国安全週間の効果を高めるため、毎年、約半年ほど前に当年の全国安全週間のスローガンが公募され、6月1日から6月30日が準備期間として設定されています。
開催数
全国安全週間の歴史は長く、昭和3年(1928年)に第1回が実施されて以来、一度も中断することなく続けられ、令和7年(2025年)で第98回を迎えます。
目的
全国安全週間は、労働災害を防止するために、産業界での自主的な活動を行うことを推進する取り組みと共に、職場での安全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的としています。
また特徴として、一部の期間を除き、スローガンが定められていることが挙げられます。令和7年度(2025年度)は「多様な仲間と 築く安全 未来の職場」となりました。
このようなスローガンを目標と掲げて、労働災害防止のための啓発活動を行います。
全国安全週間スローガン
全国安全週間スローガンは昭和19年度から35年度まではスローガンなしで進められましたが、昭和36年からは組織的な安全管理の推進を呼びかけるスローガンが復活し、文字数も増えたことでよりわかりやすくなりました。
平成に入ってからは、災害ゼロを目指す安全意識の向上やリスクの低減に重点が置かれ、個人の安全意識と組織的な取り組みの両方が強調される傾向が見られます。
また、令和に入ってからは、持続可能性や高齢化など、時代を反映したキーワードを含むスローガンが登場し、令和という新しい時代の意識変化を象徴しています。
過去の全国安全週間スローガン一覧はこちら
全国安全週間の実施内容
全国安全週間は、どのようなことを実施するのでしょうか。令和7年度全国安全週間実施要綱をもとに、期間中の実施内容について解説します。
概要
令和6年の労働災害を見ると、死亡災害は前年を下回る見通しである一方、4日以上の休業を伴う死傷災害は前年を上回ると予測されており、増加傾向が止まっていません。
なかでも、転倒や腰痛など作業行動が要因となる死傷災害や、墜落・転落による死亡災害が依然として多発しています。
こうした状況を改善し、すべての労働者が安全に働ける職場を実現するには、令和5年3月に策定された第14次労働災害防止計画に基づき、施策を着実に推進する不断の努力が欠かせません。計画の3年目となる令和7年度も、労使が一体となった取り組みが求められます。
そこで令和7年度は、「多様な仲間と 築く安全 未来の職場」をスローガンに掲げ、全国安全週間を実施します。
準備期間中と全国安全週間に実施する事項
全国安全週間実施要綱には、準備期間中と全国安全週間に実施する事項として、次のことが挙げられています。
- 安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意思の統一と安全意識の高揚
- 安全パトロールによる職場の総点検の実施
- 安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布等の他、ホームページ等を通じた自社の安全活動等の社会への発信
- 労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実施による家族への協力の呼びかけ
- 緊急時の措置に係る必要な訓練の実施
- 「安全の日」の設定の他、準備期間及び全国安全週間にふさわしい行事の実施
期間中は安全大会といったイベントを実施し、労働者に対して意識付けを行う良い機会となります。また安全パトロールによって職場を巡視し、改めて潜む危険を発見する取り組みは非常に重要です。対外的な発信や家族との協力なども日頃はなかなか行う機会のない、必要な取り組みといえます。
令和7年度の全国安全週間
最新スローガン
令和7年度の全国安全週間スローガンは以下に決定いたしました。
「多様な仲間と 築く安全 未来の職場」
令和7年度全国安全週間内容
主唱者 :厚生労働省、中央労働災害防止協会
実施者 :各事業場
準備期間:毎年6月1日~30日
本期間 :毎年7月1日~7日
令和7年度のスローガンの募集要項は以下であり、多様性の高まりに応じた安全管理、安全対策の強化を趣旨とした内容でのスローガンが募集されました。
- 製造業や建設業はもとより、高年齢労働者や外国人労働者の増加など就業構造の変化及び働き方の多様性を踏まえた安全対策の必要性も喚起できるもの
- 転倒災害や腰痛といった、労働者の行動に起因する労働災害の予防に必要な、安全意識の啓発や体づくりの必要性を喚起できるもの
- 転職等に伴う経験の少ない未熟練の労働者への安全対策の必要性を喚起できるもの
- 企業の安全管理体制の強化を奮起させるもの
全国安全週間における自主的な労働災害防止活動の事例
企業が全国安全週間において過去に行った、自主的な労働災害防止活動の事例をご紹介します。
転倒災害防止キャンペーンの実施
ある鉄鋼業の企業は、ある年の4月25日から7月7日まで、全社的に「転倒災害防止キャンペーン実施期間」と定め、指差呼称やパトロールの実施、ポスターの掲示などを行いました。
また職場の段差のある場所など、特に転倒の危険の高い場所を写真に収めて、それを小冊子にまとめる取り組みも同時に行うことで、注意喚起を強化しました。
経営層による職場安全パトロール
ある船舶事業を行う企業は、全国安全週間に経営層による職場の各部署を巡回する安全パトロールを実施しました。
普段、何気なく行っている業務をいつもとは異なる視点で確認し、不安全状態や不安全行動、潜在的危険性を取り除くことを目的としています。
具体的には安全保護具が正しく着用されているか、指差呼称などの安全行動は適切に行われているかなどをチェックしました。
現場への集中指導の実施
東京労働局では、労働災害減少を図るため全国安全週間の実施に併せて、各労働基準監督署において、建設現場に対する集中指導を実施いたします。
労働安全衛生教育も重要
全国安全週間を通して、労働災害を少しでも減らし、労働者一人ひとりが安全に働くことのできる職場環境作りを目指したいものです。
全国安全週間において、労働災害を減らすための自主的な取り組みを進めるに当たっては、参加する労働者の意識や知識を高めることで、さらなる効果を生むと考えられます。このことから、日頃からの労働安全衛生教育は重要です。
近年、労働安全衛生教育は大きく進化しています。従来の集合研修による座学に加えて、各自が空いた時間に学習できるeラーニングが取り入れられるケースが増えてきています。これまでのやり方にとらわれず、学習効果の上がりやすい方法を取り入れることで、安全意識の向上や労働災害削減に効果をもたらすでしょう。
特に動画によるeラーニング教育は、従業員が自分のペースで学ぶことができ、何度も繰り返し視聴できるため、労働安全衛生教育を効果的に実施できる教育手法として、再び注目を集めています。
全国安全週間をきっかけに、効果の上がる方法を取り入れてみるのも良いのではないでしょうか。
まとめ
全国安全週間は労働災害削減のために、従業員や社内における意識を強化し、活動をより促進するために重要な期間です。
全国安全週間期間中はもちろんのこと、日頃からの労働安全衛生教育を適切に行うことで、この全国安全週間の効果がより高まると考えられます。
効果的な労働安全衛生教育を実施したいとお考えなら、ラキールの動画配信型教育サービス「LaKeel Online Media Service」がおすすめです。
労働安全衛生などに関するアニメーションによる教育動画を700本以上提供しており、学ぶ意欲のない従業員でも興味が沸くよう工夫されているため、学びやすく理解しやすい内容となっています。
サンプル動画がございますので、アニメーションの教育動画による学びやすさ・理解しやすさを、ぜひ一度体感してみてください。
サンプルムービー
動画も見てみる!

詳細はぜひサービス紹介ページをご覧ください。
LaKeel Online Media Serviceの動画を
無料でお試しいただけます。
\1分で完了!すぐ見れる/