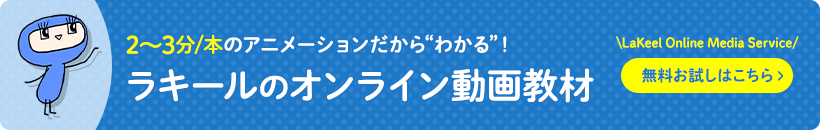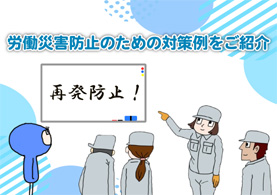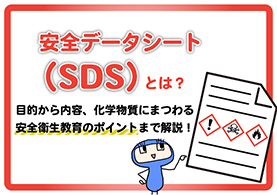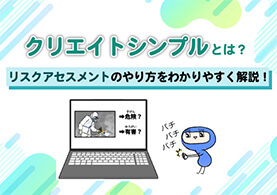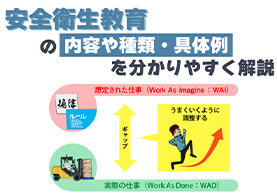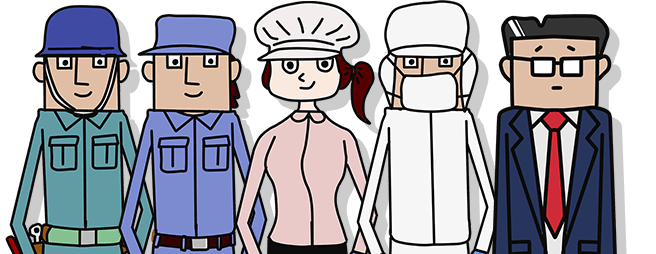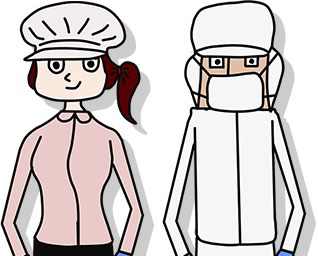労働災害を防止するためには、さまざまな取り組みを行う必要があります。実際に多くの事業場で行われていることの一つが、KYT(危険予知トレーニング)です。今回は、KYTの概要から目的、進め方や例題までご紹介します。
KYT(危険予知トレーニング)とは?
まずはKYTとは何か、その定義を解説します。
KYT(危険予知トレーニング)とは、作業自体や職場にひそんでいる労働災害につながる危険性や有害性などの危険要因を発見し、解決する能力を高めるトレーニング手法の一つです。Kは「危険(KIKEN)」、Yは「予知(YOCHI)」、Tは「訓練/トレーニング(TRAINING)」の頭文字をとって名付けられています。
KYTは、もともと大手鉄鋼メーカーで開発されたもので、中央労働災害防止協会が、職場のさまざまな問題を解決するための手法である「問題解決4ラウンド法」とKYTを結びつけました。さらに、その後、「指差呼称」を組み合わせた「KYT4ラウンド法」となり、現在はそれが標準となっています。
KYT(危険予知トレーニング)登場の背景
KYTは、もともと大手鉄鋼メーカーが、ベルギーの化学会社視察時に目にした安全衛生のイラスト表示からヒントを得て、開発した手法です。
はじめは鉄鋼会社各社で広まり、その後1973年には中央労働災害防止協会が提唱した「ゼロ災害全員参加運動」の取り組みの1つとして取り入れられたことにより、日本全国へ普及していきました。
1978年には、職場の様々な問題を解決するための手法である「問題解決4ラウンド法」と結び付けられました。
その後、「指差呼称」を組み合わせた「KYT4ラウンド法」となり、現在のKYT活動の基礎となっております。
(参考)指差呼称とは…これから作業する目の前の対象となるものや、標識や信号、計器類等に作業者が指さしを行い、その指さししたものの名称と状態を声に出して確認する危険予知活動の一種。
【関連コラム】
指差呼称(しさこしょう)とは?その効果や教育方法をご紹介
KYT(危険予知トレーニング)の目的
KYTの目的には、次のことが挙げられます。
・危険意識を高め、労働災害を未然に防止する
KYTを通して、危険に対する情報を叩きこむことで、個々の危険意識を高め、労働災害や事故防止へつなげます。
・労働環境における危険ポイントを洗い出す
KYTを通して、自社の労働環境において残存する危険のポイントを洗い出します。それにより、危険の可視化や予知、安全意識の向上を目指します。
・危険ポイントと行動目標を指差し呼称で顕在化する
KYTでは、危険のポイントや行動目標を指差す訓練を繰り返し、体が無意識に反応するほど叩き込みます。
作業の要所要所における危険に対して、都度指差し呼称で顕在化するということを習慣化することが大きな目的です。
KYTは、職場で起き得る問題や危険を先取りし、安全な労働環境を労働者と事業者が共に作り上げることが最終目的です。そしてその職場は、労働者の安全への意識が高く、明るい職場で、労働災害の発生確率を可能な限りゼロに近づける風土が根付いていることが理想です。そのような職場を作るためには、実際に問題が起きたとしても、迅速で柔軟な対応が取れる労働者の育成が必須です。
現場で予期せぬ変化や問題などの擾乱が起きても冷静に対処するには、実践の中で予想する能力、監視する能力が発揮できるように訓練をしないといけません。
KYTは、このような労働者が働く職場を築き上げていくために行います。
KYT(危険予知トレーニング)実施のメリットとは?
KYTの実施には、単に危険を防ぐだけでなく、多くのメリットがあります。例えば、イラストを活用し、実際の作業をイメージして訓練することで、危険を危険と察知する感受性が高まります。また、危険に対しての意見交換を通して問題解決能力が向上します。
他にも、暗い話題になりがちな事故や労働災害について、明るく前向きに話し合いができることにより、その話し合いの中で職場の人間関係や雰囲気が明るくなり、職場風土が変わっていくことにもつながります。
このように、KYTの実施には以下のようなメリットがあるといえます。
- 感受性が鋭くなる
- 集中力が高まる
- 問題解決能力が向上する
- 実践への意欲が高まる
- 安全先取り職場の風土づくりが実現する
また、上記に加え、KYTへの取り組みを通して個々の危険予知能力が高まり、メンバーがより自覚をもって作業に向き合うことが期待されます。
組織において、安全衛生計画の作成や管理、マネジメントといった面でもKYTの実施は良いメリットがあるといえるでしょう。
KYT(危険予知トレーニング)の進め方
事業場における一般的なKYTの進め方をご紹介します。
KYTの大まかな流れ
KYTは、主に次の流れで行います。
まず5~6人のチームを作ります。チームごとに、作業や現場の様子を示したイラストシート、弊社のKYT動画や現場の現物を使って見せ、その中にひそむ「危険要因」とそれがどのような事故を引き起こすのかを話し合います。話し合って分かり合い、もしくは1人で自問自答して、危険のポイントを確認したり、行動目標を決定したりします。
そしてポイントや行動目標を皆で指差し唱和します。実際の作業の前に指差呼称で確認し、安全を先取りします。
KYTの手順(KYT4ラウンド法の進め方)
実際の手順を確認していきましょう。
| 手順 | 概要 |
|---|---|
| はじめに | 5~6人のチームを作ります |
| 第1ラウンド 現状把握 |
環境にひそむ危険を、短時間で発見します |
| 第2ラウンド 本質追究 |
重要な危険を皆で確認します |
| 第3ラウンド 対策樹立 |
危険のポイントを解決する対策を話し合います |
| 第4ラウンド 目標設定 |
対策をしぼりこみ、行動目標として指差し唱和で確認します |
| 最後に | 実際に現場で確認する指差呼称項目を決めて締めくくります |
はじめに
まず5~6人のチームを作り、リーダーを決めます。チームごとに、作業や現場の様子を示したイラストシートや現場の現物、LaKeel Online Media ServiceのKYT4ラウンド法動画を話し合いの材料として用意します。さらには、KYT記入シートや模造紙なども用意しましょう。
第1ラウンド:どんな危険がひそんでいるか【現状把握】
どんな危険がひそんでいるかを発見する
イラストシートなどで再現された職場の環境や作業の様子などを見て、短時間でその状況の中にひそむ危険をチームメンバーそれぞれで発見し、発言し合います。発言する際には、危険要因とその要因がひきおこす現象(行動・結果)を明確にし、チーム内で共有しましょう。
【関連コラム】
不安全行動とは?不安全状態との違いから事例、対策まで一挙解説!
第2ラウンド:これが危険のポイントだ【本質追究】
危険のポイントをしぼりこむ
第1ラウンドで発見した危険のうち、重要だと思われる危険を把握して○印を付け、さらに皆の合意でしぼりこみ、◎印とアンダーラインをつけます。それを「危険のポイント」とし、皆で指差し唱和して確認します。
第3ラウンド:あなたならどうする【対策樹立】
危険のポイントを解決する対策案を話し合う
第2ラウンドで選んだ危険のポイントを解決するにはどうしたらよいかを考え、具体的な対策案を出し合います。リーダーは『あなたならどうしますか?』と問いかけ、全員で具体的な対策案を出し合いKYT記入シートや模造紙などに記入します。
第4ラウンド:私たちはこうする【目標設定】
対策をしぼりこみ行動目標として指差し唱和する
リーダーは第3ラウンドで出た複数の対策の中から、『必ず実施するとしたらどの対策にするか』と問いかけ、全員の合意のもと、対策をしぼりこみ、※印をつけ「重点実施項目」を決定します。そして、それを実践するための「チーム行動目標」を設定し、皆で指差し唱和で確認します。
最後に:確認してしめくくる
重点実施項目に関連して、実際に現場で確認する指差呼称項目を、皆の合意で決めます。そしてリーダーのリードで指差呼称項目を3回指差し唱和で確認し、タッチ・アンド・コールを行って終了です。
(参考)タッチ・アンド・コールとは…メンバー全員で手を重ね合わせたりして、触れ合いながら行う唱和のこと。円陣を作って肩に手を置き合ったり、指を握り合ったりすることで、連帯感を出す方法。
KYT(危険予知トレーニング)の例題
KYTでは、イラストシートなどを使って実際の作業を想起出来るイメージを見せることで訓練が始まりますが、より効果のある訓練を行うためにはこの教材のクオリティが重要になってきます。なるべく作業内容やどのような動きで作業を行うのか、時間の制限はどれくらいあるのかなど情報をなるべく詳しく伝えることがポイントになります。
製造業の例題の一例
材料を延ばすためのロール機械に付いた汚れを落とすため、作業者はロール機を低速回転しながら、本来、使うべき治具を使わずに汚れを拭き取ろうとしています。早く掃除を終わらせないと次の作業の開始時間がずれてしまう状況です。
・イラスト、動画の作業にはどのような危険が潜んでいるでしょうか。
・この作業を安全に実施するにはどのような対策が考えられるでしょうか。
建設業の例題の一例
鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の解体工事の現場です。作業者は今、解体で出たガラ(コンクリートの破片)などを、開口部から下の階へ降ろしています。早く作業を終わらせてみんなで飲みに行く約束をしています。
・イラスト、動画の作業にはどのような危険が潜んでいるでしょうか。
・この作業を安全に実施するにはどのような対策が考えられるでしょうか。
このようなイラストシートをチームで見ながらKYTを進めていきます。
まとめ
KYTは、労働災害を防止するために有効な手法の一種であり、長年、多くの事業場で行われている手法です。KYTをより効果的に行うためには、労働者一人一人の積極的な発言が求められます。そのためには、基本的な労働安全意識や知識が必要であることから、労働安全衛生教育に力を入れることも重要といえます。
そこで、労働安全衛生教育のツールとしておすすめなのが、ラキールの「LaKeel Online Media Service」です。
本サービスは、最新の法令に対応した労働安全衛生に関するアニメーションによる教育動画を700本以上提供しており、学ぶ意欲のない従業員でも理解しやすく、学びやすい内容となっています。また、反復性もあるため、知識の定着や行動変容を促進し、教育効果が得られやすいという特長があります。
労働者が積極的にKYTで発言するようになることが期待でき、良い影響をもたらします。
サンプル動画がございますので、アニメーションの教育動画による学びやすさ理解しやすさを、ぜひ一度体感してみてください。
サンプルムービー
動画も見てみる!

詳細はぜひサービス紹介ページをご覧ください。
LaKeel Online Media Serviceの動画を
無料でお試しいただけます。
\1分で完了!すぐ見れる/